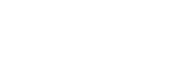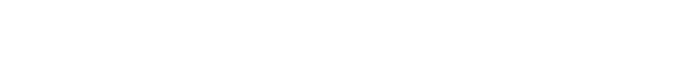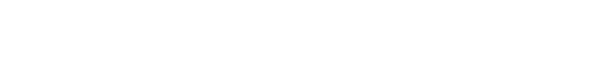相手方の財産を開示させる手続き①(財産開示手続制度)
1 はじめに
示談や裁判をして慰謝料を支払ってもらえることになったのに,相手方が支払ってこないという場合には,裁判所の強制執行手続を検討することになります(ただし,公正証書ではない示談書の場合,一旦裁判手続を経由する必要があります。詳しくはこちらのコラム「慰謝料を支払わない場合,どうなるの?」をご参照ください。)。
強制執行手続は,裁判所に差押命令の申立てをして行いますが,その申立ての際には,何を差し押さえるか特定して行う必要があります。
たとえば,給与の差し押さえであれば勤務先の情報,預貯金の差し押さえであれば金融機関名と支店名の情報が必要です。
したがって,強制執行をするには,相手方がどのような財産を持っているかがわかっている必要があります。
しかし,元夫婦といった間柄でもない限り,相手方がどのような財産を持っているか,どこに勤めているかはわからないことも多いでしょう。
これでは,せっかく裁判所の判決があっても,絵に描いた餅になりかねません。
そこで,日本の民事執行法では,財産開示手続という制度が用意されております(なお,昔は強制力の弱い制度でしたが,2020年4月1日の改正によって強化されました。)。
その他にも弁護士会照会といった方法もありますが,今回のコラムでは民事執行法上の財産開示手続制度について,横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。
2 財産開示手続制度
(1)財産開示手続制度とは
財産開示手続とは,債権者の申立てによって,裁判所が債務者を裁判所に呼び出し,債務者に自分の財産について陳述させるという手続です。
(2)裁判所の呼び出しを無視したり,嘘をつくとどうなるのか
裁判所の呼び出しを無視したり,虚偽の陳述をした場合には,6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が定められております(民事執行法第213条1項)。
実は,2020年4月1日に施行された財産開示手続制度の改正法によって,従来よりも債務者に厳しい内容と変更されました。
改正前の民事執行法でも,債務者が裁判所の呼び出しを無視して出頭しなかったり,あるいは裁判所で嘘をついた場合に,30万円以下の過料が定められておりました。過料の定めがあることで実効性が期待されていたのですが,その思惑ははずれ,それでも裁判所の呼び出しを無視するケースが多くありました(平成29年度のデータでは,約40%が不出頭でした)。
債務者の方としては,財産に強制執行をかけられるよりも,30万円の過料を支払った方が安いという考えがあったのではないかと思われます。
そのため,改正法では,裁判所の呼び出しを無視したり,虚偽の陳述をした場合に,過料30万円ではなく,6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が定められました(民事執行法第213条1項)。
なお,過料が科されても前科にはなりませんが,刑事罰は罰金であっても前科となります。債務者が裁判所の呼び出しを無視したり,裁判所で嘘をついたりすれば,前科者となるおそれがあるということです。
(3)誰が利用できるのか
財産開示制度手続を申し立てることができるのは,裁判で判決をもらった場合,調停調書がある場合,公正証書がある場合等です(2020年4月1日の改正によって対象者が増えました)。
なお,裁判外で示談をしただけでは,この制度を利用することはできません。裁判外で交わした示談書しかない場合には,一旦裁判を経由する必要があります。
(4)財産開示手続の要件
財産開示手続を利用するには,下記のいずれかの状況であることが必要とされております(民事執行法197条1項)。
ひとつめは,「申立ての日前6か月内に実施された強制執行又は担保権の実行における配当や弁済金交付手続において,申立人が当該金銭債権の完全な弁済を受けられなかったとき」です。
つまり,実際に強制執行等をしたものの,慰謝料の一部しか支払ってもらえなかったときということです。
ふたつめは,「申立人が,債権者として通常行うべき調査を行い,その結果判明した財産に対して強制執行等を実施しても,当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき」です。
つまり,まだ強制執行をしたことはないが,判明している相手方の財産を差し押さえても,慰謝料の全額には足りないことがわかっているときということです。
なお,上記の「疎明」というのは,証明ほど強くなく,一応確からしいという程度に証拠を出せば足ります。
したがって,一度は相手方の財産の調査を行う必要があります。財産調査を一度もせずにいきなり財産開示手続制度を利用することはできないということです。
具体的には,少なくとも,債務者の自宅の不動産登記事項証明書(登記簿謄本)の原本を提出する必要があります。
(5)財産開示手続は繰り返し利用できるのか
財産開示手続で,債務者が財産を開示した場合,原則として,3年以内は財産開示手続をすることができません(正確に言うと,財産開示手続を申し立てた日から3年です。)。
(6)どこの裁判所で手続するのか
相手方(債務者)の現在の住所地を管轄する地方裁判所(支部)に申立てをするのが原則です。
参考までに,神奈川県と東京都の管轄は下記のとおりです。
横浜市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・大和市・海老名市・綾瀬市・高座郡(寒川町)→横浜地方裁判所(本庁)
相模原市・座間市→横浜地方裁判所相模原市部
川崎市→横浜地方裁判所川崎支部
横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡(葉山町)→横浜地方裁判所横須賀支部
小田原市・秦野市・南足柄市・足柄上郡(中井町,大井町,松田町,山北町,開成町),足柄下郡(箱根町,真鶴町,湯河原町)
平塚市・中郡(大磯町,二宮町)→横浜地方裁判所小田原支部
厚木市・伊勢原市・愛甲郡(愛川町,清川村)→横浜地方裁判所小田原支部
東京23区→東京地方裁判所
八王子市・日野市・あきる野市・西多摩郡→東京地方裁判所立川支部
立川市・府中市・昭島市・調布市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市→東京地方裁判所立川支部
武蔵野市・三鷹市・小金井市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市→東京地方裁判所立川支部
青梅市・福生市・羽村市→東京地方裁判所立川支部
町田市・多摩市・稲城市→東京地方裁判所立川支部
3 第三者からの情報取得手続
2020年4月1日に施行された改正法により,債務者の財産を調査する方法として,「第三者からの情報取得手続」という制度が始まりました。
強制執行をしたくても相手(債務者)の財産がわからないという場合に,債務者本人ではなく,第三者から情報を取得するための制度です。
この制度については,こちらのコラム「相手方の財産を開示させる手続き②」をご覧ください。
最後までコラムをお読みいただきありがとうございます。当事務所は男女問題に注力し、年間100件を超えるご相談をいただいております。また、当事務所に所属する弁護士3名はいずれも男女問題につき豊富な経験を有しております。
男女問題にお困りの方でご相談を希望される方は、お電話または以下のリンクから初回無料相談をお申し込みください。
その他のコラム
子供から親の不倫相手に対して慰謝料請求はできるか
1 子供から不倫相手に慰謝料請求できるの? 昔から、不倫は家庭の平穏を壊すものとされてきました。不倫された方は、家庭の平穏が壊され精神的苦痛を受けるという形で被害を受けるため、不倫相手に対して慰謝料を請求することができるとされています。 それでは、夫婦の間に子供がいた場合はどうでしょうか。子供も不倫によって家庭の平穏を壊され、被害を受けているといえそうです。 子供は親の不倫相手に対して慰謝料請求ができるのでしょう...
不貞相手に請求できるのは慰謝料だけ?
1 はじめに 不貞相手に請求できるものは慰謝料以外にはないのでしょうか。例えば,調査のために探偵費用を支払った場合や,慰謝料を請求するのに弁護士に依頼した場合の費用,精神的ショックによる通院費用など不貞の発覚によりかかる費用には様々なものがあります。 本コラムでは,法律上,不貞相手に対してどのような名目の費用が請求できるか,またいくらまで請求が認められるのかを解説をしていきます。 2 探偵費用 ...
離婚後に元配偶者の不貞が発覚。今からでも慰謝料請求はできる?
1 はじめに 不貞の発覚をきっかけに離婚をする夫婦は多いですが、中には離婚後に元配偶者の不貞が発覚するという場合もあるでしょう。 そのような場合であっても、不貞慰謝料請求はできるのでしょうか。 今回はこの疑問について、横浜シティ法律事務所の弁護士が解説いたします。 2 不法行為であることに変わりがない 結論から申し上げますと、離婚後に元配偶者の不貞が発覚した場合であっても、慰謝料請求ができる可能性があ...
ゴールデンウィーク期間中の営業について(2025年)
横浜シティ法律事務所の令和7年(2025年)のゴールデンウィーク期間中の営業と、ご相談の予約方法について、ご案内いたします。 営業日と休業日 横浜シティ法律事務所は、以下のとおり、暦どおりの営業となります。 4月28日(月) 通常どおり営業 4月29日(火) 休業 4月30日(水) 通常どおり営業 5月1日(木) 通常どおり営業 5月2日(金) 通常どおり営業 5月3...
不倫のせいで別居・離婚になっても,面会交流はできる?
1 面会交流とは? 面会交流とは,離婚に際して親権者とならなかった親が,子供と会ったり,文通したり,電話したりして交流することをいいます。最近では,メールやライン,写真や動画の送付といった交流のかたちも増えております。 また,離婚をしておらず,夫婦が別居している場合に,子供と一緒に暮らしていない親が,子供と会ったりすることも同様に面会交流といいます。 2 不倫があっても面会交流は求めていいの? ...